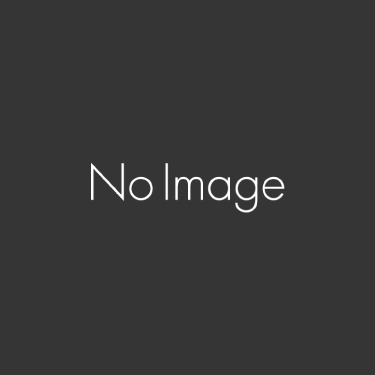2017年、イエナプラン教育専門教員養成研修に参加した私の初めての実習先は、フェーンダムという街にある イエナプランスクール イン・デ・マネ(In de Manne)でした。ここは、0~2年生/3~5年生/6~8年生(4~12歳)の異年齢学級がそれぞれおよそ3クラス。全員が平屋の校舎に収まる適度なサイズ感から、家庭的だけれどダイナミックな印象も受ける学校でした。
このイン・デ・マネに滞在する期間中、私はこの学校にお子さんを通わせている保護者の方のお宅にお世話になりました。ホストマザーに初めて会ったのは、車で私を迎えに来てくれた時。無事に家に着くと、彼女は早速3階部分にあたる屋根裏部屋に私を通してくれました。
「あなたの部屋はここよ。自由につくろいでもらっていいのよ」
などと(たぶん)言ってくれたと思います。私は持ち合わせのオランダ語(英語のやりとりがほとんどだったので、結局指で数えられる程の単語しか覚えていなかった)で「Dank u wel(ありがとう)」と答え、大きな期待と少しの不安の入り混じったような思いで、ベッド脇に荷物を置きました。しばらくすると、
「ダイスケ、下に降りて来て。家の中を案内するわ」と彼女。「オーケー!」と応じ、私は1階へ降りて行きました。
通されたのはリビング。中央に家族が食卓を囲める長方形のテーブルがあり、奥の窓の外には芝生の小さな庭が見えました。反対側には壁を隔てずにソファーとテレビ、それに子どもの玩具や誕生日をお祝いするための(?)カラフルなケーキのオブジェが置かれたスペースが広がっていました。
私が降りてくると、家族の一員の黒茶色の子犬(ダックスフント?)がリビングを駆け回り、突然の来客に思いきりのいいタックルをかましてきました。「あっちに行きなさい!」と言ったかどうかはわかりませんが、彼女は子犬をリビングの奥の小部屋のようなスペースに軽く追い込みました。そして、
「この部屋にも食料があるのよ。フルーツとか、シリアルとか。何か食べたいものがあったら、自由に取ったらいいわ」と言いました。でも、私は内心こんな風に思っていました。
(ありがたいなあ。けど、そうは言っても、ちょっとここのは取りづらいな。犬いるし…)と。
それから、彼女は子犬をその場に残して扉を閉め、すぐ正面のキッチンに向かいました。
「あなた、料理はする? ここにある道具も全部自由に使っていいのよ」
「Oh, really!? I like cooking.(ホント!? 料理は好きだよ)」と私。
(蕎麦とか持ってきてるから、一回は日本料理でも振る舞ってお礼をしたらいいな…)などと想像をしていると、
「それから、」と、ホストマザーは冷蔵庫の扉を開けながら、少しビックリする私に、こう言いました。
「この中の食材も飲み物も、全部あなたものだと思って、自由に食べたり飲んだりしていいわよ。自分の家だと思って、楽にしてくれたらいいのよ」
(ええっ!?)
ここまで来ると、さすがに驚きました。日本では、そもそもホームステイを受け入れること自体に抵抗を持つ家庭がほとんどでしょう(もちろん、オランダでも一定の割合ではいるのかもしれませんが)。それに、受け入れたとしても、冷蔵庫の中身まで見せて「自分のものだと思っていい」とまでは、さすがに言わないと思うのです。仮に、私が日本でそう言われたとしても、当時ならきっと、
(ああ、ありがたいなあ。でも、これはあくまで <建前> であるから、気持ちだけ受け取っておいて、本当に中のものが欲しい時には、念のため一声かけるようにしよう…)
と思っていたでしょう。しかし、不思議なことに、このとき私が受けた感覚は、それとは全く異なっていました。私はこう感じました。
(ああ、この人は、私に本当にそうしてもらいたいんだ。そうやって、私が自分の家にいるように寛いでいることが、この人にとっても本当に心地良い、ということなんだ…!)
このとき、私はオランダという国が教育の多様性を保障し続けられる理由の一端に触れた気がしました。それは全くシンプルなことで、この国の人たちは <本音> で話している、ということでした。使ってもらっては困るものは「使わないで」と言うし、一向に構わないものについては「自由にして」と言う。人はそれぞれに違う。だから、他人のことをどれだけ想像してみても、その全てが当たることなどあり得ない。それならば、自分が思っていることは互いに率直に言葉にし合おう、ということなのでしょう。
さて、そろそろ、こんな言ってみれば当たり前のことを多弁に書き連ねているのが、なんだか滑稽に思えてきました。何故なら、この文章をホストマザーやオランダで出会ったイエナプランナーたちが読んだら、きっと
「だって、そうしないとわからないでしょ?」と、真顔で答えるに違いないからです。
「いや、全くその通り。そうしないとわからない。でも、私たち(日本人)はそうして来ていない、ということなんだよ…」
そう、脳内の私は半ば自動的に返答します。すると、私の中の彼女たちは、すかさずこう返してきました。
「じゃあ、そうしたらいいんじゃない?」と。
さあ、この球、どう返しましょう。
「いや、わかるけど、そう単純なものじゃないんだ…」
こう返して、悲哀と憂いに満ちたラリーを続けるのも、無駄なこととは思いません。何故なら、そういう思索は、私たちが社会をより深く理解する助けになり得ると思うからです。でも、久しぶりにこの原稿を書きながら、オランダの人たちを想って懐かしんでいたら、今日の私はシンプルにこう返して、決着をつけたくなりました。
「うん、そうだね」
本音と建前、どちらに近づこうとするのか。私はオランダで出会った人たちに、それをいつも問われている気がするのです。(濵 大輔)