- 1
- 2
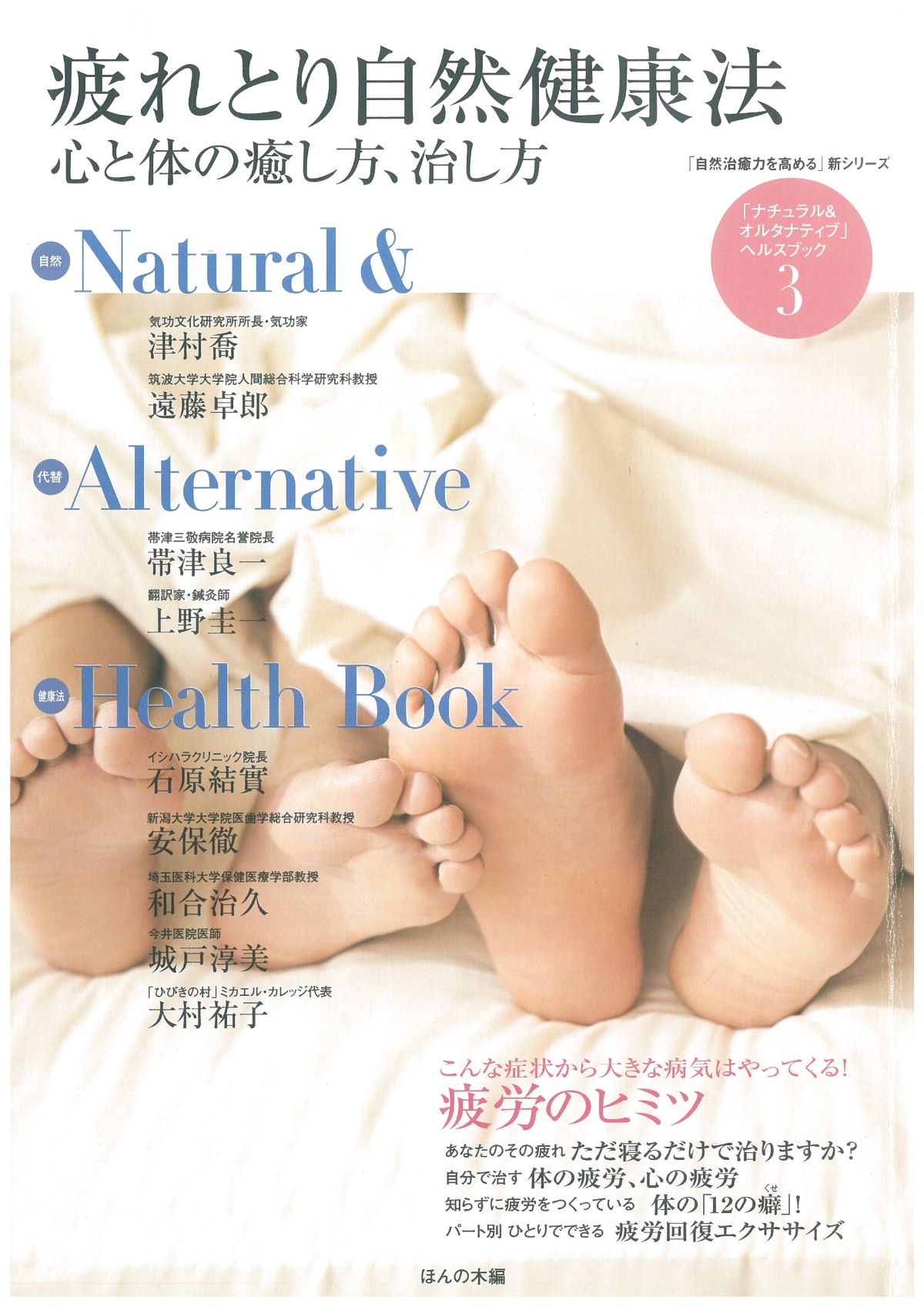 ポッドキャスト「健康やり直し倶楽部」第3回では、雑誌「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」第3号の「疲れ取り自然健康法」を特集。高橋編集長が、専門家の見解を一覧にした画期的な目次構成や、「疲労」をテーマにした意図、数値化されない健康の捉え方の重要性を語ります。また、社会運動家・津村喬氏の寄稿や、具体的なエクササイズについても触れ、「疲れ」との向き合い方のヒントを探ります。
ポッドキャスト「健康やり直し倶楽部」第3回では、雑誌「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」第3号の「疲れ取り自然健康法」を特集。高橋編集長が、専門家の見解を一覧にした画期的な目次構成や、「疲労」をテーマにした意図、数値化されない健康の捉え方の重要性を語ります。また、社会運動家・津村喬氏の寄稿や、具体的なエクササイズについても触れ、「疲れ」との向き合い方のヒントを探ります。
【出演者】
川村さん:司会
高橋さん:「ナチュラル&オルタナティブ ヘルスブック」編集長、株式会社ほんの木代表
第3回のテーマは「疲れ取り自然健康法」
川村さん:
健康やり直し倶楽部、今回で3回目となります。
高橋編集長、よろしくお願いします。
高橋さん:
どうぞよろしくお願いいたします。
川村さん:
第3回目となる今回は、「疲れ取り自然健康法 心と体の癒やし方・治し方」というテーマですね。
これは以前の雑誌になりますが、第1回、第2回と続き、第3回目で私が一番驚いた、素敵なアイデアだと思ったのは、雑誌でいう「表2」(表紙の裏ページ)の部分です。
ここが、今回の冊子に寄稿されている先生方の要約というか、コメントが入った目次になっていて、一覧形式で紹介されています。
これは非常に画期的なアイデアだと感じたのですが、どのような意図でお作りになったのでしょうか?
画期的な目次の工夫とその意図
高橋さん:
このアイデアは、第1号、第2号にはありませんでした。
今、手元に第3号と第4号がありますが、第4号にも同様の形式が採用されています。
私たちもこの本を作るにあたっては、本当に試行錯誤の連続でした。
例えば食の問題を考えたとき、牛乳は飲んだほうがいいのか、飲まないほうがいいのか、というように、一つのテーマに関しても、専門家の方々の中でも様々な考えがあり、時には矛盾するテーマである可能性もあります。
そこで、読者の方に、各執筆者がどのような考えを持っているのか、何を提唱しているのかを、まずインデックスのように一覧で見ていただき、関心のあるテーマから読んでいただくことで、この本の使い勝手が良くなるのではないかと考えました。
最初に問題提起と要約、そして可能であれば結論まで示したいと考えましたが、結論まで出し切るのは難しく、途中で終わっている部分もあります。
それでも、各執筆者の見解を示すことで、読者の理解を深められると考え、第3号からこの形式を始めました。
川村さん:
なるほど。
いわば、各記事の「つかみ」のような役割を果たしているということですね。
高橋さん:
まさにその通りです。
「つかみ」という表現がぴったりです。
川村さん:
この形式は読者にとって非常に分かりやすいですし、編集という観点から見ても、このような試みはもっとあっても良いのではないかと感じました。
なぜ「疲労」をテーマに?
川村さん:
さて、今回の第3号についてですが、第1回、第2回では「なぜ病気になるのか」や「胃腸」といったテーマでお話を伺いました。
今回は、それらよりもさらに身近な、「疲れをどうするか」という、より根源的な問題の手前にあるテーマを取り上げている点が非常に興味深いと感じています。
「疲労とは何か」という、よくよく考えると捉えどころのないテーマに切り込んでいる点がユニークだと思ったのですが、第3号で「疲労」というテーマを選ばれたのは、どのような意図があったのでしょうか?
高橋さん:
なぜ第3号で「疲労」を取り上げたのか、明確な理由を申し上げるのは難しいのですが、健康を考える上で、まず「食べること」が重要だと考え、第2号で「食」をテーマにしました。
その前、第1号では「ホリスティックヘルスとは何か」という、健康の全体像をテーマにしました。
次に、異なる視点から健康を捉えるテーマとして、「体」についてもう少し深く考えたいと思いました。
代替療法やホリスティックな視点から健康を捉える際、西洋医学のように数値を可視化する方法もありますが、数値化しなくても、自分の体の声に耳を傾けることで、その人なりの健康状態を把握できるのではないかと考えました。
そのような視点からテーマを集め、今回の特集に至りました。
社会運動家・津村喬氏の寄稿
川村さん:
少し私事になりますが、今回、久しぶりに懐かしいお名前を発見しました。
津村 喬(つむら たかし)さんです。
少し驚きました。
私たちの世代、1970年代に学生だった者にとっては、ある種のスターというか、社会運動の中で輝いていた方のお一人でしたので、「あっ、津村さんだ」と。
津村さんが政治的な活動から離れ、気功などに関心を移されたという話は風の便りに聞いていましたが、この雑誌に寄稿されているとは知りませんでした。
ここで再会できたような気持ちです。
残念ながら2020年にお亡くなりになったのは、本当に残念ですが、この津村さんを執筆者として起用された経緯はどのようなものだったのでしょうか?
高橋さん:
津村さんは、肩書としては医療関係者ではありません。
川村さんがおっしゃるように、社会運動家、あるいは思想家といった方です。
世の中を深く捉えてこられた津村さんが目指していたのは、社会全体の、そして個人の「自然治癒力を高めること」ではないかと考えていました。
社会の自然治癒力を高める一環として、個人のあり方も重要だと考え、津村さんの生き方や当時の活動についてお話を伺うことにしました。
実際に伺ってみると、津村さんは気功家として、体のあり方を深く研究し、実践されていました。
専門的な医療とは異なりますが、しっかりとした背景に基づいた、非常に分かりやすいお話を伺うことができました。
これは具体的な実践例として紹介したいと考え、この本の中で、津村さんと相談しながら具体的なエクササイズ方法をパターン別に紹介しています(28ページ以降)。
今、改めて読み返してみて、私自身ももう一度やってみようと思うほど、分かりやすく実践的な内容にまとめられた記憶がよみがえってきました。
「休むこと」の重要性
川村さん:
あまり個人的な見解を深く話すと政治的な話になりそうなので避けますが、1970年代の社会変革の流れの中で、食や文化など様々なものがカウンターカルチャーとして見直される動きがありました。
その中で、政治的な活動に疲れた人々が内面的な探求に向かうという流れも、津村さんが気功のような道に進まれた一因かもしれません。
それはさておき、私自身、趣味でトライアスロンをやっているのですが、走る、泳ぐ、自転車をこぐといったトレーニング以上に、「休むこと」、つまり「いかに疲れを取るか」が、長く競技を続けていく上で非常に重要だと実感しています。
ですから、この「疲労を取る」というテーマには非常に興味があり、記事を読ませていただいています。
体を鍛えること以上に、体を癒やす、休むことが、いわばバランスを取る上で非常に大切なのではないかと感じているのですが、その点はいかがでしょうか。
- 1
- 2

